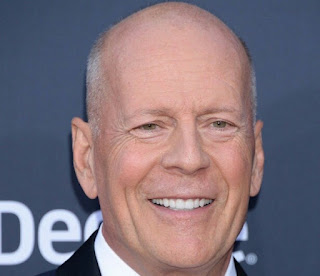1972年 アメリカ。
当時、あの『ゴッド・ファーザー』と並んで大ヒットした作品。
破格の製作費を上回って、莫大な興行収入を得るほどの大ヒット。
淀川長治さん(日曜洋画劇場)、水野晴郎さん(金曜ロードショー)、荻昌明さん(月曜ロードショー)など映画評論家たちは、こぞって、この映画を大絶賛。
自分達の番組で、代わりばんこに、常に放送していたくらいだった。(そのくらい、当時は、二時間映画の枠は多かったのです)
特に、淀川先生の溺愛ぶりはスゴくて、
「私は、この映画に出会う為に、産まれてきた!」なんて言っていたくらい。(まぁ、何事にも大ゲサなのが映画評論家なんですけどね)
《パニック映画》なんて呼称は、この映画から、始まったんじゃなかったかな。
で、……………こんな大ヒット作には必ずといっていいほど、付いてくるのが続編、そしてリメイク。
『ポセイドン・アドベンチャー2(1979)』
『ポセイドン(2006)』、
全部、見事にコケました。(他にもテレビドラマで3時間のモノもあるらしいが……)
《パニック映画》というのを、予期せぬ未曾有の災害が襲って、「ワァー!ワァー!」人々が騒ぎながら、逃げまくるだけのモノだと勘違いしているから、こうなるのである。
「大迫力の災害シーンを上手く描けば、ヒットは間違いなし!」
なんて思い込んでいる映画関係者たちは、大勢いるはず。
そんな人々は、少しばかり映画を読み解く力や分析力が甘いんじゃないかな?
でも、それだけじゃないのが、この傑作『ポセイドン・アドベンチャー(1972)』なのです。
豪華客船《ポセイドン号》は、大晦日の明け方、荒れ狂う波の中を何とか、やり過ごしながら突き進んでいた。
『ハリソン船長』(レスリー・ニールセン)は、最初から、この《ポセイドン号》の航海には、一抹の不安を抱いていたのだが、その予見が、見事に当たった感じだ。
船の重心が高すぎるのだ。
船の重心が高ければ、安定させるために、バラスト(底荷)をして、船底を重くしなければならないのに、それもしていない。
大波がくれば、一発で転覆する恐れもある。
スピードを出すことも、もはや危険だったのだが…………
「何をモタモタしているんだ?さっさと全速前進しろ!もう、3日も到着が遅れているんだぞ!!お前をクビにしてもいいんだぞ!!」
船主代理人の男が、船長の横で、ギャン!ギャン!わめき散らしている。
(この……ド素人が………どうなっても知らんぞ)
そんな豪華客船《ポセイドン号》には、様々な乗客たちがいる。
過激な説教を持論にしている『スコット牧師』(ジーン・ハックマン)は、アフリカの未開地に左遷されて、そこへ向かう為に乗り込んでいる。
「神に祈るだけで寒さがしのげるか?!寒さをしのぐなら、『燃やせるモノは何でも燃やせ!』それが私の持論だ!!」(いいのか?こんな過激な思想の牧師って?)
幼い弟『ロビン』(エリック・シーア)は、姉の『スーザン』(パメラ・スー・マーティン)と共に、両親の元へ帰省するために乗りこんでいた。
ロビン少年は、もっか、この《ポセイドン号》の構造や機能に夢中になっている。
「この船のエンジン馬力はすごいんだよ!機関室だって凄い設計なんだから!!」
両親からきた電報を読みながら、スーザンは知らぬ顔。
(全く……変わり者の弟なんだから……何がそんなに面白いのかしら?………)
老年のローゼン夫婦は、イスラエルの孫に会うために乗船中。
「もう、どんなに大きくなってるかしら?2歳になってるはずよ。楽しみだわ」
太った妻『ベル・ローゼン』(シェリー・ウィンタース)は、お昼の甲板で編み物をしながら、まだ見ぬ孫に、想像を膨らませてウキウキ。
その横では、夫の『マニー・ローゼン』(ジャック・アルバートソン)は、「わしは、モーセが十戒を受けたという山のツアーに行きたいんだがね……」なんて、ひとり言をブツブツ。
夫妻の目の前を、雑貨屋を営んでいる『マーチン』(レッド・バトンズ)が運動不足にならないよう、ジョギングして通りすぎた。
「あの人、イイ感じよねぇ~独り者なのかしらねぇ~?」(出たー!バァ様のお節介)
大晦日を祝う為の大広間では、それぞれテーブルが並べられて、ボーイたちが、その支度にバタバタしていた。
「おい!何をボーッとしてる?」
仲間のボーイに急かされてもエイカーズは、美人歌手『ノニー』(キャロル・リンレイ)の歌声に聞き惚れている。
「いいねぇ~、良い歌だねぇ~………」
「おい!早く出てこい!何をそんなに手間取ってるんだ!?パーティーが始まるんだぞ!!」
『マイク』(アーネスト・ボーグナイン)は、自室の化粧室に閉じ籠って、出てこない妻『リンダ』(ステラ・スティーヴンス)を心配して、大声をあげていた。
マイクは元刑事で、リンダは元娼婦。
二人は異色の組み合わせの夫婦だった。
「うるさいわね!いい加減にしてよ!!」
リンダは出てくると、浮かない顔をしている。
「いったいどうしたんだ?」
リンダはポツリと呟いた。
「いるのよ………この船の中に……昔、私の客だった男が………だから、パーティーに出たくないのよ」
「それが何だ!昔の事だろう。気にしなければいいさ!!」
「何よ、それ!あんたったら私を6回も逮捕したくせに!!」
「あんな商売を辞めさせたかったからだ!文句あるか!」
言葉は荒くても、リンダにベタ惚れのマイクである。(この顔で、純粋なオッサンを演じさせたらボーグナインは、さすがに上手いなぁ~)
そんなマイクの一途さに打たれて、リンダも堅気になる決心をしたのだ。
そんなマイクの一途さに打たれて、リンダも堅気になる決心をしたのだ。
「分かったわよ、パーティーに行きましょう」
何が起きても動じそうもないマイクの愛情が通じたのか、リンダの気持ちも軽くなったようだ。
そうして、大晦日のパーティーがはじまる………。
こんな個性豊かな面々たちが、この後、大方の予想通り、大災害に出合うのである。
《ポセイドン号》は、地震の津波で、大波をくらい、転覆。
船は、まっ逆さまにひっくり返って、船底が持ち上がった状態になる。
「キャーーーー!!」、
「ワァーーーーー!!」
テーブルが、椅子が、ひっくり返って、人間たちが逆さまになった船の中で、なぎ倒されていく。
大勢の人々が亡くなっていくのだが、そんな中で、冒頭に書いた登場人物たちの個性が激しくぶつかり合う、人間ドラマが繰り広げられていくのである。
そう、『パニック映画』とは、『集団人間ドラマ』なのだ。
災害も、迫力ある津波も、その背景の、ほんの一部でしかないのだ。
パニック状態の中、スコット牧師は皆のリーダー格となって叫びだす。
「船が沈む前に、船底に向かって、皆で上がっていくんだ!」
それに反対する者たち。
「馬鹿な!無謀だ!!助けが来るまで、動かないで待った方がいい!!」
反対する者、賛成する者に別れて、意見は真っ二つ。
冒頭に書いた登場人物たちは、スコット牧師に賛成して、船底に上がる為に無我夢中になって、死に物狂いで進んでいく。
そして、後に残った者たちは、案の定、海水にのまれて死んでいく。
選択肢を間違ったばかりに………。
極限状態では、ナビも、全く役に立たない。
人生の選択肢は、「右に行くのか?」、「左に行くのか?」、いつも分かれ道に立たされていて、二つにひとつ。
それを選んで進んでいくのは、自分の考え、ひとつなのである。
失敗するかもしれない……あの時、違う道を進んでいたなら、今の自分の境遇は、ガラリと違うものになっていたんじゃないか………そんな後悔に想いをはせる人もいるはずだ。
この『ポセイドン・アドベンチャー』は、それを、我々にまざまざと観せて、考えさせるのである。
稀代の映画評論家たちが、こぞって褒めたたえるのも、分かる気がする。
個性豊かな人間たちが、上手く描かれているか、どうか………それが重要なキー・ポイントであり、一番大事な事。
そして、『パニック映画』に至っては、それが普通の映画と違って、大人数となるのだから、脚本家や監督たちは、よくよく考えてから、手を出してくださいね。
迂闊に手を出してしまうと、その人の才能や力の差が歴然と分かってしまうので(笑)。
それくらい、敷居の高~い、難しいジャンルだと思って頂きたい。
それらを、全てクリアして、成功している、この『ポセイドン・アドベンチャー』は、まさに金字塔。
星☆☆☆☆☆であ~る。
※全5種の日本語吹き替えが入ったBlu-rayが発売されております。
色々、聴き比べて観てみたいものですね~♪