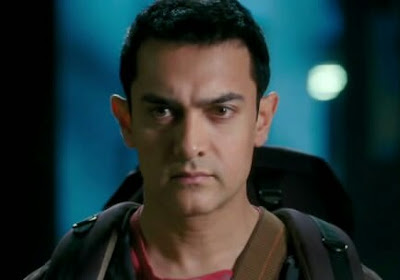写真家の『ファルファーン』(R・マドハヴァン)は、インドから飛び立つ飛行機の機内にいた。
あと、もう少しで飛行機は離陸する。また、しばらくは故郷インドともお別れだ。
そんな時、いきなり携帯に電話。
大学の時の同級生で、嫌味な『チャトル』(オミ・ヴァイディア)からだ。
何事かと思い、しぶしぶ電話にでると、
「ランチョーを見つけた!すぐに大学に来い!」チャトルは、それだけ言うと電話を切った。
(ど、どうすればいい?飛行機は間もなく飛び立つ………)
慌てたファルファーンは、機内で咄嗟に倒れこみ、仮病をつかって強引に飛行機を止めた。(いいのか?)
飛行場を降り、これまた強引にタクシーを拾うと、大学時代の親友『ラージュ』(シャルマン・ジョシ)に即、電話する。
「今から迎えに行くから、表で待ってろ!ランチョーが見つかったんだ!」
ベッドで、まどろんでいたラージュも、寝間着のまま慌てて飛び起きた。
着の身着のままのラージュをタクシーで拾い、大学の屋上に向かうと、嫌味なチャトルが仁王立ちで待ち構えていた。
「10年前の約束を覚えているか?」嫌味なチャトルは、屋上の柱に書かれた文字を指さし続ける。
「俺は絶対にお前らより成功してみせる!と誓った。そして、そのとおりに成功したのだ!!ガッハハハッ!」ファルファーンもラージュもチャトルの出世話には興味なし。それよりも………
目的はランチョーの事だけなのだ!
「ランチョーはどこなんだ?!」
いらつき質問する二人に、「シムラだよ」とチャトルは、やっと答えた。
3人はチャトルの車で、すぐさま遠いシムラの町を目指して出発。
ファルファーンは車を走らせながら、10年前を思い出していた……
かけがえのない永遠の友、ランチョーに初めて出会った日の事を………。
―― 10年前。
ファルファーンは、ICE(インド屈指の難関な競争率の工科大学)に、ギリギリの成績で入学してきた。
本当は写真家になりたかったファルファーンだが、エンジニアにしたい父親には、到底さからえない。
寮の同室には、彼もまた、ギリギリの成績で入学してきたラージュがいた。
寝たきりの父親と、それを世話する母親、いき後れの姉……一家の生活は困窮していて、全ての期待が、ひとり息子のラージュに、のしかかっていたのだ。
「無事に卒業して、なんとしても立派な会社に就職せねば!……」
そんなプレッシャーと闘いながら、部屋中を御守りなどで飾り立てていて、「神様、どうか、無事に卒業できますように!」と祈りに必死である。
学生の世話係で働いている、小柄な通称ミリメーターは、ファルファーンの荷物を運びながら、
「今夜は綺麗なパンツを穿いていなよ!」と助言した。
同室の二人は「???」だ。
だが、その理由はすぐ分かった。
夜になると、全員の新入生がパンツ一枚の姿にさせられ、上級生にお尻をつきだし、牛の刻印ごとく、スタンプを押されるのだ。(難関の大学にしては、そうとう変な恒例行事だ)
上級生に逆らえない新入生たちは、頭ではバカバカしい行事と思いながらも、パンツ一枚で、手を差し出し、
「王よ、どうか、お受け取りを!」と口々に言わなければならない。(繰り返すが、変態行事である (笑) )
そこへ、一人の新入生が遅れて現れた。
ランチョルダース・シャマルダース・チャンチャル、(な…長い名前)通称『ランチョー』(アーミル・カーン)だ。
周りの状況にキョトン顔のランチョーに、新しい獲物を見つけた上級生はご機嫌だ。
「さあ、お前もパンツ一枚になれ!」
だが、ランチョーは、それを無視して、素早く自室に閉じこもってしまう。
「出てこい!出てこないとお前のドアにオニュー(小便)をかけるぞ~!」上級生の男が、扉を叩きながら、はやし立てている。(どんな変態上級生? (笑) )
ランチョーは、部屋のブレーカーを落とし、配線をつなげたスプーンを棒に結び固定した。
扉の下の隙間から、そのスプーンをソーッと、差し出すランチョー。
それに上級生がオニュー(小便)をかけた時に、勢いよくブレーカーをあげた。
電流はスプーンから~小便を上へと伝わり~上級生の股間のイチモツを直撃した!!
「ギャアアアアア―ッ!」
絶叫をあげながら、悶絶して倒れ込む上級生。
初めてみたインド映画。
そして、凄い面白かった!!
そして、凄い面白かった!!
近年、観た映画の中でも、この映画は確実に、自分のマイ・ベストテンの上位に食い込むだろう。
泣かせて、笑わせて……自分が欲しているようなモノが、全て、ここにつまっているような、そんな奇跡のような映画である。
このタイトル「きっと、うまくいく」が、ピッタリで、近年にしては中々センスの良い邦題。(原題は「3バカ」らしいが、これじゃ、日本では受けなかっただろう)
「きっと、うまくいく!」は、主人公ランチョーの口癖なのである。
テストでも、神頼みで祈ってばかりいるラージュにも、
「胸に手を当てて、こう言うんだ。『うま~くいく、うま~くいく』」と。
産まれた時から、親にレールをひかれ、エンジニアになるべくして、大学に入ってきたファルファーンにも、写真家を目指すように、同じようにさとす。
学歴や順位優先の大学側にも、ランチョーは、独自の考えで、変革を訴え続けるのだ。
そんな異端児ランチョーを校長の『ウィルス』は、いつも目の敵にしている。
もじゃもじゃヘア(石立鉄男風)に、いつも苦虫を潰したような顔をしているウィルス校長。
ウィルスは絶対的権力で、ランチョーたちを、色々な手をつかっては追い詰めるが、ランチョーは、そのハードルを軽々クリアしていくところに、この映画の爽快感がある。
だが、青春には、馬鹿な事をしたり、くだらないイタズラも、時には充分ありだ。
ウィルス校長の長女の結婚式に、招待もされていないのに、只飯にありつく為に、変装して浸入したり……。
ウィルスの次女『ピア』は、そんな馬鹿な事を繰り返すランチョーを、最初は嫌っていた。
だが、ランチョーの、友達思いな気持ちや、自分への優しい気づかいに触れるうちに、徐々に好意を持ちはじめていく。
「あたし、この人好きかも……」って思ってしまったピアの妄想は、みるみる膨れ上がり、いきなり歌って踊ってのミュージカルに発展するのはご愛敬。(これぞ!まさしくインド映画って感じだけどね)
それにしても、このランチョーは普段は何事にも動じないのだが、友達の為なら、よく泣いている。
こんなに泣く主人公も珍しい。
そして、このランチョーが涙すれば、同級生のファルファーンもラージュも、そしてピアも、ランチョー(アーミル・カーン)を好きにならずにいられない。
もちろん映画を観ている我々もだ。
青春は、「涙」と「少しばかりのイタズラ」……。
星☆☆☆☆☆です。